如何お過ごしですか? 3回連続10cmです。
当ブログにお越しいただきありがとうございます。
いつも本当にありがとうございます。
忘れもしない26年前の平成7年1月17日。
私は直接被害を受けていません。
そんな私が心の部分をあれこれ書くのはアレなので、あの時の人々の色々な想いを風化させてはいけない、とだけ書いておきます。
ここでは、その兵庫県南部地震の後、同年6月に発行された橋梁の専門書を紹介します。
余談:当日の朝のこと。
5時40分頃急に目が覚めました。
しばらくして揺れました。
高松でも震度3か4だったと思います。
当日は仕事で川之江へ行く用事があり高速に乗ってラジオを聞いていました。
当然特番で速報が出るたびに死者が100人単位で増えていき恐ろしくなったのを覚えています。
復旧仕様。
正確には【「兵庫県南部地震により被災した道路橋の復旧に係る仕様」の準用に関する参考資料(案)】という長ったらしい名前です。
我々は略して復旧仕様と呼んでいました。
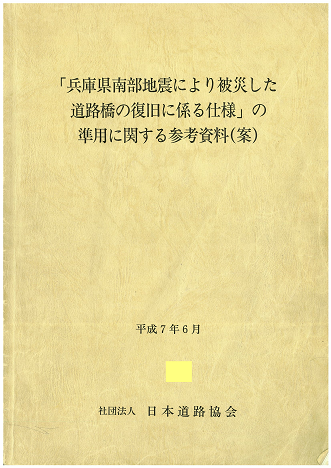
復旧仕様のまえがきに書かれていること。
兵庫県南部地震においては、道路橋に大きな被害を生じたことから、建設省(現国土交通省)では地震直後に被災原因の究明と今後の耐震設計のあり方等の検討を目的に、耐震工学、橋梁工学等の専門家からなる兵庫県南部地震道路橋震災対策委員会(委員長:岩崎敏男(財)建設技術研究所理事長)を設置したところである。
「兵庫県南部地震により被災した道路橋の復旧に係る仕様」(以下、復旧仕様という。)については、兵庫県南部地震道路橋震災対策委員会の審議を経て、2月27日に関係機関に通知されたところであり、さらに、5月25日には、橋、高架の道路等の技術基準(道路橋示方書)の改定が行われるまでの当面の措置として、全国で今後実施される新設橋梁の設計および既設橋梁の補強についても復旧仕様を参考とする旨が通知されたところである。
このような中で、3月30日の兵庫県南部地震道路橋震災対策委員会の中間報告において、今後の耐震設計で検討すべき事項が取りまとめられたのを受け、日本道路協会橋梁委員会においては震災対策特別分科会を設置し、今回の被災を踏まえた橋、高架の道路等の技術基準の内容についての検討を進めるとともに、活動の一環として、復旧仕様の準用に関する検討も進めてきた。
本参考資料は、復旧仕様を準用して新設橋梁の設計や既設橋梁の補強を出来るだけ円滑に行うことができるよう、設計計算例とこれを行う際に参考となる補足事項をとりまとめたものである。
日本語ですか?って話だけど、要約すると
①地震がおこった。
②原因究明・今後の耐震設計のあり方を検討するために委員会を作った。
③その委員会が復旧仕様というものを作った。
④次回の道路橋示方書(=橋の基準書)改定までは、現行基準書でなくて復旧仕様を準用しろ。
⑤本書は復旧仕様に準拠した計算例が載ってるからそれで設計しろ。
ということです。
設計する観点からいうと
橋梁は通常、道路橋示方書(=橋の基準書)に準拠して設計するんだけど、
現行の基準書には今回の地震の事が加味されていないので、
新しい基準書が出来るまでは復旧仕様で設計しろ。
ってことです。
新しい基準書は平成8年12月に発行。
当時現行の基準書は平成6年のもので、当然この平成6年の基準で橋を作っていました。
この復旧仕様が出来た平成7年6月からは暫定的に復旧仕様で橋を作りました。
新しい基準書は平成8年12月に出来ました。

ですので1年半の間復旧仕様で橋が作られたことになります。
平成8年12月以降は、復旧仕様も盛り込まれた新しい基準書で橋が作られています。
その後基準書は平成14年に改定されたので、約7年間はこの復旧仕様が生きていたということになります。
編集後記
復旧仕様、いかがでしたか?
復旧仕様自体はマニアックすぎてアレなんですが、
橋梁設計業界も地震の事例を踏まえて色々検討しているということだけ、それとなくお分かりいただけたら幸いです。
ちなみに平成23年の東北大震災の後も、より強靭な橋が出来るよう平成24年に新しい基準書が発行され、それに準拠して橋が作られています。
